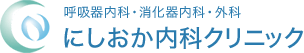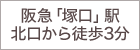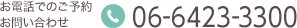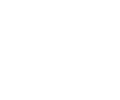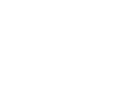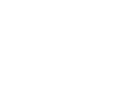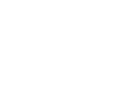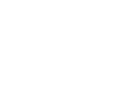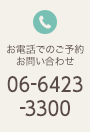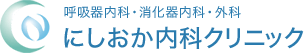- 長引く咳でお悩みの方へ
- 咳を止まらない時には?
- 咳を軽く見ないで!命に関わる重篤な病気の可能性も
- 咳の原因を正確に知るための検査
- 咳の治療方法について
- 咳を和らげる生活習慣の改善
- 咳を予防するためにできること
- 咳が続くとき、医療機関を受診すべきタイミングは?
- よくある質問(FAQ)
長引く咳でお悩みの方へ
「風邪かも」と思って放置していませんか?その咳、病気のサインかもしれません
咳(せき)は、体が外からの異物や刺激を排除しようとする自然な防御反応です。例えば、ホコリや煙、ウイルス、細菌などが気道に入り込むと、これらを外に出そうとして咳が起こります。この働きによって、呼吸器が守られ、私たちの健康が保たれているのです。
しかし、この咳が何日も続いて止まらない、あるいは数週間経っても良くならないといった場合には注意が必要です。咳が長引くことで生活の質が低下し、仕事や学業に支障が出ることもありますし、なにより重大な病気が隠れている可能性があるからです。
咳には大きく分けて、「急性咳嗽(3週間以内)」「遷延性咳嗽(3〜8週間)」「慢性咳嗽(8週間以上)」の3つのタイプがあります。短期間でおさまる咳であれば、風邪などの一時的な感染症であることが多いですが、3週間を超えても症状が続く場合には、感染症以外の原因も疑う必要があります。
特に、痰が絡まず乾いた咳が続く、夜間や早朝に咳がひどくなる、会話中や笑った後に咳き込むといった特徴が見られる場合、単なる風邪ではなく、喘息や咳喘息、アレルギー、逆流性食道炎など、ほかの疾患が原因である可能性が考えられます。
咳を止まらない時には?
咳の原因を探ることが、適切な治療への第一歩です
咳が長引く背景には、さまざまな病気が存在しています。ひとくちに「咳が続く」と言っても、その原因はひとつではありません。
感染症が引き起こす咳
まずもっとも一般的なのが、風邪やインフルエンザなどの感染症です。風邪のウイルス(ライノウイルスやRSウイルスなど)が喉や気道に炎症を起こすことで咳が出ます。通常、風邪による咳は1〜2週間ほどで治まることが多いですが、感染後も気道の炎症が残ってしまうと、咳だけが長く続くこともあります。
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症では、咳とともに高熱や全身のだるさを伴うことが特徴です。特に新型コロナは、軽症でも咳だけが長引くケースが報告されており、注意が必要です。
さらに、気管支炎や肺炎、百日咳、肺結核といった呼吸器の感染症も咳の原因となります。これらの病気では、痰を伴う咳が多く、発熱や胸の痛み、呼吸の苦しさを伴うことがあります。百日咳は強い発作的な咳が特徴で、特に夜間に激しくなることがあります。肺結核の場合、長期間にわたる咳や微熱、体重減少などが見られ、近年は再び増加傾向にあるため、注意が必要です。
アレルギーによる咳
アレルギー体質の方は、日常の環境の中にあるアレルゲンに反応して咳が引き起こされることがあります。特に近年増えているのが、咳喘息(せきぜんそく)やアトピー咳嗽(あとぴーがいそう)と呼ばれる病気です。
咳喘息とは?
咳喘息は、通常の喘息のような「ゼーゼー、ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)を伴わない咳が特徴です。主に乾いた咳が続き、夜間や早朝、運動後に悪化する傾向があります。原因は、ハウスダスト、ダニ、花粉、ペットの毛、冷たい空気などのアレルゲンや刺激物に対する気道の過敏反応です。咳喘息を放置すると、本格的な喘息に進行することもあるため、早期の診断と治療が大切です。
アトピー咳嗽とは?
アトピー咳嗽もまた、アレルギーが関係する咳のひとつで、咳喘息とよく似ていますが、気管支拡張薬が効かないという点で区別されます。咳は乾いたタイプで、喉のイガイガ感や違和感を伴うことが多いです。抗アレルギー薬や抗ヒスタミン薬が有効です。
鼻の病気が咳の原因になることも
鼻の症状が原因で咳が出るケースもあります。代表的なのが後鼻漏(こうびろう)と呼ばれる状態です。これは、鼻水が喉の奥に落ちていくことで喉の粘膜を刺激し、咳が出るといものです。特に横になったときに咳が悪化することが多く、「夜になると咳が出る」「朝起きたときに咳が出る」といった訴えが見られます。
また、副鼻腔気管支症候群(ふくびくうきかんししょうこうぐん)も、咳の原因として注目されています。これは、慢性副鼻腔炎と慢性気管支炎が合併して起こる状態で、痰のからんだ咳が長期間にわたり続くのが特徴です。適切な抗生剤治療や鼻の治療が必要になります。
胃酸の逆流による咳(GERD)
胃食道逆流症(GERD)は、胃の内容物(特に胃酸)が食道に逆流することで、咳を引き起こすことがあります。これは、胃酸が食道や喉の粘膜を刺激するだけでなく、逆流物が気道に入り込む(誤嚥)ことでも咳が誘発されるためです。
GERDによる咳は、特に食後や横になった時に強くなる傾向があり、胸焼けやのどの違和感を伴うことがあります。逆流を防ぐためには、生活習慣の見直しと胃酸を抑える薬による治療が効果的です。
咳を軽く見ないで!命に関わる重篤な病気の可能性も
咳が長引く原因として、比較的多く見られる風邪やアレルギーだけでなく、注意が必要な重篤な病気が隠れている場合もあります。
気胸(ききょう)〜若年層にも起こる、突然の胸の痛みと咳
気胸とは、肺に穴があいて空気が胸腔に漏れ、肺がしぼんでしまう病気です。これにより、咳や胸の痛み、呼吸困難が引き起こされます。特に痩せ型の若い男性に多く見られますが、喫煙者にも多く発症するため注意が必要です。
症状は突然起こることが多く、「急に胸が痛くなって息がしづらくなった」「片側の胸に圧迫感がある」といった訴えで来院されることも珍しくありません。軽度であれば自然に治癒する場合もありますが、中等度以上の場合は胸腔ドレナージなどの治療が必要となります。
肺がん〜長引く咳は、がんのサインであることも
咳が慢性的に続く場合、肺がんの可能性も考慮する必要があります。日本では肺がんはがんによる死因の第1位であり、喫煙者はもちろん、非喫煙者でも腺癌というタイプの肺がんにかかることがあります。
肺がんの初期症状としては、「痰のない乾いた咳」「血の混じった痰(血痰)」「声のかすれ」「体重減少」「胸の痛み」などがあります。特に1ヶ月以上咳が続く場合や、血痰が出る場合は精密検査が必要です。早期に発見すれば、治療の選択肢も広がります。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)〜タバコが引き起こす進行性の病気
COPDは、主に長年の喫煙によって肺の機能が低下する病気で、慢性気管支炎や肺気腫を含む総称です。最初は軽い咳や痰、階段を上がったときの息切れといった症状が現れますが、進行すると少しの動作でも息が苦しくなるようになります。
この病気の怖いところは、気づいたときにはかなり進行していることが多い点です。在宅酸素療法が必要になるケースも多く、日常生活の質を大きく損ないます。喫煙歴が長く、咳や痰が慢性的にある方は、一度呼吸機能検査を受けることをおすすめします。
間質性肺炎〜進行すると呼吸が苦しくなる病気
間質性肺炎とは、肺の組織(間質)に慢性的な炎症が起こり、線維化が進むことで呼吸がしづらくなる病気です。原因としては自己免疫疾患(膠原病)や喫煙、職業性粉塵などが挙げられますが、原因不明(特発性)のものも少なくありません。
乾いた咳(空咳)や息切れが主な症状で、初期は風邪と区別がつきにくいため注意が必要です。病気が進行すると、酸素の取り込みが難しくなり、在宅酸素療法が必要になることもあります。
心不全〜心臓の不調が引き起こす咳
意外に思われるかもしれませんが、咳の原因が心臓の機能低下(心不全)であることもあります。心不全では、心臓から血液を十分に送り出せなくなるため、肺に水がたまりやすくなり、咳や息切れを引き起こします。
夜間や横になると咳がひどくなる、足のむくみがある、疲れやすいといった症状がある場合は、心臓の検査も視野に入れる必要があります。
咳の原因を正確に知るための検査
一人ひとりの症状に合わせた診断がカギです
咳が続く原因を特定するためには、複数の検査を組み合わせて行います。当院では、以下のような検査を通して、患者さん一人ひとりに最適な診断と治療を行っています。
- 問診・身体診察
まずは症状の詳細を丁寧にお聞きします。咳の出方(乾いた咳か、痰を伴うか)、時間帯、誘因(運動後、食後、夜間など)に加え、喉の痛み、熱、倦怠感などの随伴症状についても伺います。聴診では、肺の音(ラ音)や呼吸音の異常を確認します。 - 胸部X線検査(レントゲン)
肺炎や肺がん、心不全、肺結核などの可能性を調べるために、胸部のX線写真を撮影します。比較的短時間で結果が出るため、最初に行う基本的な検査の一つです。 - 胸部CT検査
X線でわかりにくい微細な病変や、間質性肺炎、早期の肺がんの診断には、より詳細な画像が得られる胸部CTが有効です。当院では受診当日に胸部CT検査を実施できる体制を整えています。
- 呼気NO検査
喘息の診断に有効な検査です。呼気中の一酸化窒素濃度を測定することで、気道のアレルギー性炎症の有無を評価できます。非侵襲的で痛みもなく、短時間で終わる検査です。 - 呼吸機能検査(スパイロメトリー)
呼吸の強さや量を測ることで、気道の狭窄(せまくなっているかどうか)を判断します。喘息やCOPDの診断や重症度の評価に用いられます。 - 血液検査
血液中の好酸球数、IgE値、CRPなどの炎症マーカーを測定することで、アレルギーや感染症の有無を確認します。必要に応じて、結核や膠原病などの精密な検査も実施します。
咳の治療方法について
原因に合わせた的確なアプローチが、回復への第一歩です
咳の治療は、「咳そのものを止めること」が目的ではなく、「咳の原因となっている病気を治すこと」が基本となります。咳は体が発しているSOSサインですので、原因を明らかにし、それに応じた治療を行うことが大切です。
薬物療法
咳の原因となる病気に応じて、以下のような薬が用いられます。
- ウイルス性の風邪による咳
特別な治療薬は必要ないことが多く、対症療法として咳止め薬(鎮咳薬)や去痰薬を使用します。咳止め薬は、咳を抑える効果がある薬で、特に夜間の睡眠が妨げられるような場合に使われます。 - 細菌感染(気管支炎、肺炎など)
抗生物質が必要になります。症状や検査結果を見ながら、細菌の種類に応じた薬剤を選択します。 - 喘息や咳喘息の場合
気道の炎症を抑えるために、吸入ステロイド薬を使用します。さらに、気管支を広げる気管支拡張薬が併用されることもあります。これらの吸入薬は毎日継続することで効果を発揮します。 - アトピー咳嗽やアレルギー性鼻炎に伴う咳
抗アレルギー薬や抗ヒスタミン薬が処方されます。これにより、気道のアレルギー性炎症を抑えます。 - 後鼻漏が原因の咳
鼻の治療を中心に行います。点鼻薬や抗ヒスタミン薬、去痰薬などが用いられます。 - 副鼻腔気管支症候群
抗菌薬の長期投与が必要となる場合があります。慢性副鼻腔炎が原因の場合には耳鼻科での治療が並行して行われることもあります。 - 胃食道逆流症(GERD)による咳
胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)が使用されます。あわせて、食後すぐに横にならない、夜遅くの食事を避けるといった生活習慣改善も重要です。 - COPDに伴う咳
吸入ステロイドや長時間作用型の気管支拡張薬などが使用されます。状態が進行している場合には、在宅酸素療法が必要になることもあります。 - 間質性肺炎
原因が特定できれば、その治療(たとえば自己免疫疾患に対する免疫抑制療法)を行いますが、原因不明の特発性間質性肺炎の場合は治療が難しく、進行を抑えるための薬剤投与が中心となります。 - 心理的な要因による咳の場合
身体的な異常が見つからず、ストレスや不安が関与していると考えられる場合には、心理的なサポートが重要です。リラクゼーション法、カウンセリング、場合によっては抗不安薬や抗うつ薬などの処方が検討されることもあります。
咳を和らげる生活習慣の改善
日々のちょっとした心がけで、咳の軽減や予防が可能です
咳を引き起こす要因は、生活環境の中にも潜んでいます。
- 禁煙・受動喫煙の回避
タバコは、気道に炎症を起こし、慢性的な咳の原因となります。特にCOPDや肺がん、間質性肺炎など喫煙がリスク因子となる病気が数多くあるため、禁煙は咳治療における最重要項目と言えます。また、周囲の人の煙(受動喫煙)にも注意が必要です。 - 室内環境の整備
乾燥した空気は、喉や気道を刺激し咳を引き起こす要因になります。加湿器を使用して、室内の湿度を50〜60%に保つことが推奨されます。また、ホコリやハウスダストを取り除くために、こまめな掃除や空気清浄機の利用が効果的です。 - アレルゲンへの対策
アレルギーによる咳が疑われる場合は、原因となるアレルゲンとの接触をできるだけ避けることが大切です。花粉症の季節には外出時にマスクを着用する、帰宅後はうがいや洗顔をする、衣類についた花粉を室内に持ち込まないといった対策が有効です。 - 食生活の見直し(逆流性食道炎の対策)
食べ過ぎや就寝直前の食事により、胃酸の逆流が起こりやすくなります。食後はすぐに横にならず、就寝まで2〜3時間は空けるよう心がけましょう。脂っこい食事やカフェイン、アルコールの摂取も控えるとよいでしょう。
咳を予防するためにできること
ちょっとした工夫が、咳を遠ざけるカギになります
- こまめな手洗い・うがい
風邪やインフルエンザなどの感染症を予防するために、外出後や食事前後の手洗い・うがいは非常に有効です。 - マスクの活用
花粉やハウスダスト、PM2.5などの吸入を防ぐことができます。風邪をひいている人の飛沫感染予防にもなります。 - 適度な湿度と換気
加湿器の使用で室内を適度な湿度に保ち、定期的に窓を開けて新鮮な空気を取り入れるようにしましょう。 - 規則正しい生活
睡眠不足や過労は免疫力を低下させ、感染症にかかりやすくなります。バランスの良い食事、十分な睡眠、ストレスの管理も重要です。
咳が続くとき、医療機関を受診すべきタイミングは?
このような症状がある場合は、早めの受診をおすすめします
- 1週間以上咳が続いて軽快しない場合
風邪なら通常1週間程度で改善します。改善の兆しが見られない場合、他の疾患を疑うべきです。 - 胸の痛みや息苦しさを伴う咳
気胸や心不全、肺炎などの可能性があります。緊急性が高いため、早めの受診が必要です。 - 血の混じった痰(血痰)が出る
肺がんや結核などの可能性もあるため、早期に受診してください。 - 咳とともに38度以上の発熱が数日続く
細菌感染の可能性があり、抗生剤が必要になる場合がありますので早期に受診してください。 - 夜間に咳が悪化して眠れない
咳喘息やGERDの可能性があります。生活に支障が出る場合は治療が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 咳が1週間以上止まりません。様子を見ても大丈夫ですか?
A. 咳が1週間以上続く場合は、風邪以外の疾患の可能性もあるため、早めの受診をおすすめします。特に夜間に悪化する、痰がからむ、発熱があるなどの症状がある場合は注意が必要です。
Q2. 市販薬で咳を止めても大丈夫でしょうか?
A. 市販薬は一時的に症状を緩和することができますが、根本的な原因を治すことはできません。症状が長引く場合は必ず医療機関を受診しましょう。
Q3. 子どもの咳も長引くことがありますか?
A. はい。特にアレルギーや喘息があるお子さんは、夜間や運動後に咳が長引くことがあります。呼吸が苦しそうな場合や眠れないほどの咳がある場合は、小児科を受診してください。(※当院では高校生以上の方を対象に診療を行っています)
Q4. 喘息と咳喘息の違いは何ですか?
A. 喘息は「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴や息苦しさを伴うのに対し、咳喘息は咳だけが続きます。どちらも吸入薬による治療が有効ですが、咳喘息は放置すると本格的な喘息に進行することもあります。
Q5. 咳が出ると肺がんが心配です。どのような咳が要注意ですか?
A. 長期間続く咳、血の混じった痰、体重減少、声のかすれなどがある場合は、肺がんの可能性もあります。特に喫煙者は早期にCT検査を受けることをおすすめします。
Q6. 胃酸の逆流が原因で咳が出ることがあると聞きました。本当ですか?
A. はい。胃酸が食道を通って喉に達することで刺激となり、咳が出ることがあります。食後や夜間に悪化する咳はGERD(食堂医逆流症)の可能性があるため、内科での診察を受けましょう。
Q7. アレルギー体質ですが、咳が出るのは花粉の時期だけです。受診すべきですか?
A. 花粉が気道を刺激して咳が出ることもあります。アレルギー性鼻炎が関係している可能性があるため、抗アレルギー薬の処方が有効なこともあります。一度ご相談ください。
Q8. 呼吸機能検査はどんなことをするのですか?
A. スパイロメーターという機器を使って、息をどれだけ深く吸い、どれだけ速く吐き出せるかを調べます。喘息やCOPDの診断に役立ちます。
Q9. 喫煙者ですが、咳が出ても病院には行っていません。問題ありませんか?
A. 喫煙者の咳は「たばこ咳」と言われ見過ごされがちですが、COPDや肺がんの可能性もあります。年齢や喫煙歴に応じて定期的な検査を受けることをおすすめします。
Q10. 咳が出たら何科を受診すればよいですか?
A. 咳の診療は内科または呼吸器内科が基本です。当院では、咳に関する症状を幅広く診療しており、必要に応じて検査も迅速に対応しています。
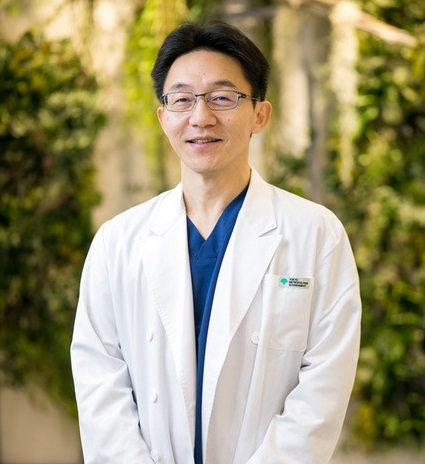
にしおか内科クリニック
院長 西岡 清訓
(にしおか きよのり)
- (元)日本呼吸器外科学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会指導医・専門医
- 日本外科学会専門医
- 麻酔科標榜医・がん治療認定医