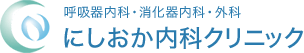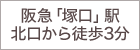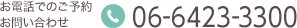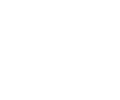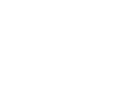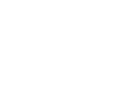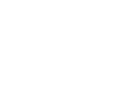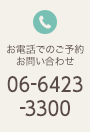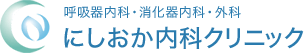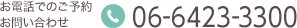「排便のたびにお尻が痛い…」「トイレのたびに血が出る…」「長時間座っているのがつらい…」
こうした肛門のトラブルに悩んでいる方は、もしかすると「痔」かもしれません。
実は痔は、日本人の約3人に1人が一度は経験すると言われている非常に身近な病気です。しかし、「恥ずかしい」「誰にも相談できない」といった理由で、我慢し続けてしまう方も少なくありません。
今回は、「痔の正しい治し方」をテーマに、自宅でできるケアの方法から、病院での治療、生活習慣の改善まで、わかりやすく解説いたします。正しい知識を持ち、早めに対処することで、症状の改善や再発防止につながります。
痔とは?まずは3つのタイプと原因を知ろう
痔には主に3つの種類があり、それぞれ原因や症状が異なります。自分の症状にあったケアを行うためには、まず痔の種類を理解することが重要です。
・痔核(じかく)〜いわゆる「いぼ痔」
最も一般的なのが「痔核」です。肛門周辺の血管がうっ血し、イボのような腫れができる状態です。
便秘でいきみすぎたときや、長時間座った姿勢が続いたときなどに発症しやすく、排便時の出血や痛み、違和感が特徴です。
軽度であれば自宅でのケアで症状を和らげることができますが、重度になると脱肛(肛門の外に出てしまう)や激しい痛みを伴うことがあります。
・裂肛(れっこう)〜通称「切れ痔」
裂肛は、肛門の皮膚が切れてしまった状態です。硬い便が無理に通過したときや、便秘や下痢を繰り返すことで、皮膚が裂けることが原因です。
排便時に鋭い痛みを感じるのが特徴で、排便が怖くなってしまい、さらに便秘が悪化するという悪循環に陥ることもあります。
・痔ろう(じろう)〜膿がたまってトンネルができる状態
痔ろうは、肛門の奥にある腺に細菌が入り込み、膿がたまって通路(ろう管)ができてしまう病気です。
自然に治ることはなく、外科的な治療が必要となるケースが多いため、早めの受診が重要です。
発熱や腫れ、強い痛みを伴うことが多く、他の痔とは異なる治療アプローチが必要です。
自宅でできる!痔の症状を和らげるケア方法
の多くは、早期の段階であれば自宅でのケアや生活改善で症状の悪化を防ぎ、自然に回復することも可能です。
・痔核(いぼ痔)の自宅ケア
痔核の症状をやわらげるには、まず血流をよくすることがポイントです。
40度程度のぬるま湯に10〜15分ほど浸かる温坐浴を毎日続けることで、肛門周辺のうっ血を改善し、炎症や痛みを和らげることができます。
また、排便のときにいきみすぎないように心がけましょう。便意を我慢すると便が固くなり、いきみの原因になります。便意を感じたらすぐトイレへ行き、無理のない排便を心がけることが大切です。
排便後は、トイレットペーパーでゴシゴシ拭くのではなく、シャワーやぬるま湯でやさしく洗浄して清潔を保つようにしましょう。
痛みや腫れがある場合は、市販の痔用軟膏や坐薬を使用することで症状を軽減できます。
・裂肛(切れ痔)の自宅ケア
裂肛は、硬い便や頻繁な排便によって生じるため、便を柔らかく保つことが最大のポイントです。
まずは食物繊維をしっかり摂り、水分を十分に補給しましょう。
野菜、果物、海藻、豆類などを意識して食べ、1日1.5〜2リットル程度の水分を取ると効果的です。
また、香辛料やアルコールなどの刺激物は肛門に炎症を起こしやすいため、症状がある間は控えるようにしましょう。
市販の軟膏には、傷の治りを助ける成分や、痛みや炎症を抑える成分が含まれているものもあり、裂肛の改善に役立ちます。
我慢せず受診を
自宅でのケアだけでは症状が改善しない場合や、出血が続く・痛みが強いといった症状がある場合は、医療機関での治療が必要です。
・薬物療法(内服薬と外用薬)
排便をスムーズにするための便秘薬(緩下剤や膨張性下剤)、腸内環境を整える整腸剤などを使い、排便時の肛門への負担を減らします。
また、外用薬としては、炎症を抑えたり、痛みを和らげたりする軟膏や坐薬が処方されます。
これらの薬は症状のタイプや重症度によって異なるため、自己判断で市販薬を使用し続けるのではなく、医師の診察を受けて処方された薬を使用することが安心です。
・痛みを和らげる日常の工夫
痔の痛みを軽減するために、自宅での過ごし方にも配慮が必要です。
たとえば、長時間同じ姿勢で座っていると肛門周辺の血流が悪くなり、症状が悪化することがあります。
デスクワーク中は1時間に1回程度立ち上がって軽くストレッチを行うなど、血行を促すよう意識しましょう。
また、入浴はぬるま湯を使用し、体を温めて血流をよくすることで、痛みや違和感を緩和する効果が期待できます。炭酸ガス系の入浴剤などを使うのも良い方法です。
食事から見直す!痔の改善と予防に役立つ食生活
痔の予防と改善において、食生活の見直しは欠かせません。
便秘や下痢の原因となる食事内容を見直し、腸にやさしい食生活を心がけることで、痔の悪化を防ぐことができます。
食物繊維は便のかさを増やし、排便をスムーズにします。野菜や果物、きのこ、豆類、全粒粉のパンや雑穀ごはんなどを取り入れると良いでしょう。
水分補給も大切で、1日を通してこまめに水やお茶を飲むことで、便の水分量を保ち、硬くなりにくくなります。
乳酸菌(ヨーグルトや発酵食品)は腸内環境を整える働きがあり、便秘改善に効果的です。
再発を防ぐために気をつけたい生活習慣
痔は、治ったとしても再発しやすい病気です。症状を繰り返さないためには、日常生活の中での工夫が重要になります。
・便意を我慢しないこと
便がたまると硬くなり、いきみに繋がります。感じたらすぐにトイレへ。
・長時間のトイレ滞在を避けること
スマホや読書をしながら長く座ると、肛門に圧力がかかりやすくなります。
・冷え対策をすること
体が冷えると血行が悪くなり、痔が悪化しやすくなります。腹巻きや温かい飲み物を活用しましょう。
・ストレスを溜めないこと
自律神経の乱れは、便秘や下痢を引き起こし、痔の原因になります。リラックスする時間を意識的に作ることも大切です。
病院を受診すべきタイミングとは?
次のような症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診してください。
- 排便時の出血が多い、止まらない
- 激しい痛みや腫れがある
- 排便が困難である
- 膿が出てきたり、発熱がある
- 1週間以上症状が改善しない
特に「痔ろう」が疑われる場合は、早期の手術が必要になることもありますので、放置せず、専門医の診察を受けましょう。
肛門ケアの基本 痔の予防と再発防止の第一歩
痔を防ぐには、日頃の肛門ケアも欠かせません。排便後にトイレットペーパーで何度も強く拭くと、皮膚を傷つけてしまい、炎症の原因になります。
できるだけ温水洗浄便座を活用し、やさしく洗い流した後、やわらかいトイレットペーパーで軽く水分を拭き取るようにしましょう。
温水洗浄便座を使用する場合は、水圧を弱めに設定し、使用時間は短くすることがポイントです。
まとめ 痔は早めの対処と生活改善で治すことができます
痔は、決して恥ずかしい病気ではありません。むしろ、多くの方が経験する身近なトラブルのひとつです。
自宅での正しいケアや生活習慣の見直しによって、初期の痔であれば改善することが十分に可能です。
しかし、症状が長引いたり悪化したりしている場合は、我慢せずに肛門科や内科を受診することが、早期回復への最短ルートです。
当院では、患者さまの症状に応じた適切な治療と、生活改善のアドバイスを行っています。お一人でまず、まずはお気軽にご相談ください。
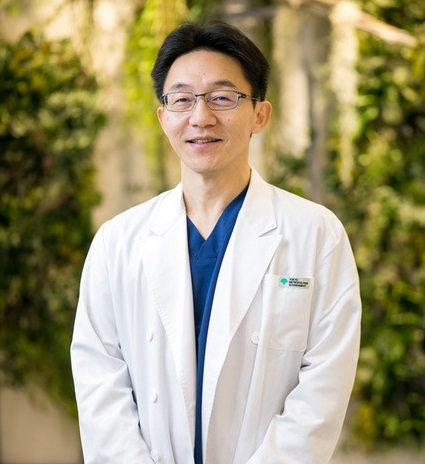
にしおか内科クリニック
院長 西岡 清訓
(にしおか きよのり)
- (元)日本呼吸器外科学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会指導医・専門医
- 日本外科学会専門医
- 麻酔科標榜医・がん治療認定医