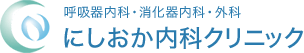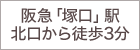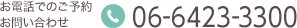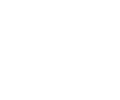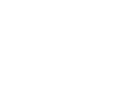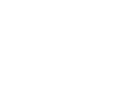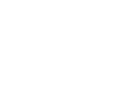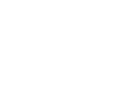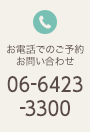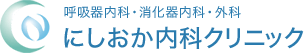肛門のトラブルは日常生活の中で見過ごされがちですが、実は多くの方が抱えている問題です。特に痔は年齢や生活習慣に関係なく発生しやすく、適切な知識と早期の対処が重要です。今回は、痛くない痔と痛い痔の違いや種類、症状、原因、そして効果的な治療法について詳しく解説します。
痔の種類と特徴
痔には大きく分けて3種類あり、それぞれ症状や痛みの程度が異なります。
- 内痔核(ないじかく)は、肛門の内側、直腸粘膜下にできる痔です。特徴として、いぼ状の突起ができ、排便時に出血することが多いものの、痛みをほとんど感じません。これは内痔核ができる部位に痛覚神経が少ないためです。進行すると肛門から脱出することがあり、その状態を「脱肛」と呼びます。
- 外痔核(がいじかく)は、肛門の外側、肛門縁の皮下にできる痔です。血栓を伴うことが多く、急激に腫れて強い痛みを引き起こします。触ると硬いしこりとして感じられ、座ることも困難になるほどの激痛を伴うことがあります。
- 裂肛(れっこう)は、いわゆる「切れ痔」のことで、肛門の皮膚に亀裂や傷ができる状態です。排便時に鋭い痛みを感じ、紙に鮮血が付着することが特徴です。慢性化すると肛門が狭くなり、さらに排便が困難になる悪循環に陥ることがあります。
痛くない痔と痛い痔の違い
痛くない痔の代表例は内痔核です。肛門の内側にできるため、初期段階では自覚症状がほとんどありません。主な症状は排便時の出血で、便器が真っ赤になるほど出血することもありますが、痛みはほとんど感じません。進行すると、ぷにぷにとした柔らかいいぼ状の突起が肛門から出てくることがあり、違和感や残便感を覚えるようになります。
一方、痛い痔の代表例は血栓性外痔核や裂肛です。血栓性外痔核は、肛門周囲の静脈に血栓ができて急激に腫れる状態で、激しい痛みと腫れを伴います。特に座っているときや排便時に強い痛みを感じ、歩くことも困難になることがあります。裂肛は排便時に肛門が切れることで生じ、排便中から排便後にかけて鋭い痛みが続きます。
痔の原因と進行のメカニズム
痔の主な原因は、肛門周囲の血流障害と圧力の増加です。便秘により硬い便を無理に排出しようとすると、肛門周囲の静脈に過度の圧力がかかり、血管が拡張して痔核を形成します。また、下痢を繰り返すことで肛門の粘膜が傷つき、裂肛の原因となることもあります。
長時間の座位や立位も痔の原因となります。デスクワークや運転手など、同じ姿勢を長時間続ける職業の方は特に注意が必要です。妊娠中は胎児の重みで骨盤内の血流が悪くなり、痔になりやすくなります。
食生活も大きく影響します。食物繊維不足や水分不足は便秘を引き起こし、痔の発症リスクを高めます。アルコールや香辛料の過剰摂取も肛門周囲の血管を拡張させ、痔の悪化につながることがあります。
痛くない痔の正体とは?
痛くない痔は主に内痔核で、直腸粘膜下の静脈が拡張してできる静脈瘤です。この部位には痛覚神経がほとんど存在しないため、かなり進行するまで痛みを感じることがありません。初期段階では排便時の出血のみで、多くの方が「痔かもしれない」と思いながらも放置してしまいます。
内痔核は進行度により4段階に分類されます。第1度は出血のみ、第2度は排便時に脱出するが自然に戻る状態、第3度は脱出後に手で押し込む必要がある状態、第4度は常に脱出している状態です。痛みを感じ始めるのは、通常第3度以降で、脱出した内痔核が肛門括約筋で締め付けられたときです。
いぼ痔と内痔核の違い
「いぼ痔」という言葉は一般的に使われますが、医学的には内痔核と外痔核の両方を指すことがあります。いぼ痔という呼び名は、肛門周囲にできるいぼ状の突起を表現したもので、その位置により内痔核か外痔核かに分類されます。
内痔核は肛門の内側にできるため、初期は外から見えません。進行して脱出すると、ぷにぷにとした柔らかい突起として触れることができます。一方、外痔核は最初から肛門の外側にでき、硬いしこりとして触れることが特徴です。
治し方と改善方法
痔の治療は、症状の程度により保存的治療から外科的治療まで幅広く選択されます。
生活習慣の改善は、すべての痔に対する基本的な治療です。食物繊維を豊富に含む野菜や果物を積極的に摂取し、1日1.5~2リットルの水分補給を心がけます。排便時は無理にいきまず、便意を感じたらすぐにトイレに行くことが大切です。また、長時間の座位を避け、1時間に1回は立ち上がって軽く体を動かすことも効果的です。
薬物療法では、炎症を抑える軟膏や座薬、内服薬を使用します。軟膏は肛門周囲に直接塗布し、座薬は肛門内に挿入して使用します。内服薬には、便を柔らかくする緩下剤や、静脈の循環を改善する薬剤などがあります。
痔の治療法
保存的治療で改善しない場合は、より積極的な治療が必要となります。
ジオン注射療法(ALTA療法)は、内痔核に硬化剤を注射して縮小させる治療法です。日帰りで施行可能で、痛みもほとんどありません。効果は高く、多くの患者さんで症状の改善が見られます。
外科手術は、重症例や他の治療法で改善しない場合に選択されます。痔核を切除する「痔核切除術」や、肛門の緩んだ組織を切除して縫い縮める「PPH法」などがあります。手術は確実性が高い反面、術後の痛みや回復期間を要するため、適応は慎重に判断されます。
手術が必要なケース
手術が必要となるのは、保存的治療で改善しない場合や、日常生活に著しい支障をきたす場合です。具体的には、第3度・第4度の内痔核で脱出を繰り返す場合、血栓性外痔核で激痛が続く場合、慢性裂肛で肛門狭窄を起こしている場合などです。また、痔瘻(じろう)という肛門周囲に膿の通り道ができる病気を合併している場合も、手術適応となることがあります。
痛くない痔を放置するリスクと進行・合併症
痛くない痔だからといって放置すると、徐々に症状が進行します。内痔核は脱出を繰り返すうちに、粘膜が傷つきやすくなり、出血量が増加します。また、脱出した内痔核が戻らなくなる嵌頓(かんとん)状態になると、血流が遮断されて壊死を起こし、激痛を伴うようになります。
慢性的な出血は貧血の原因となり、めまいや倦怠感、動悸などの症状が現れることがあります。また、痔の症状だと思っていたものが、実は大腸がんなど他の疾患である可能性もあるため、自己判断は危険です。
痔の予防
痔の予防には、日常生活の改善が最も重要です。
食事面では、食物繊維を1日20~25g摂取することを目標にします。野菜、果物、海藻類、きのこ類などをバランスよく摂り、白米を玄米に変えるのも効果的です。水分は1日1.5~2リットルを目安に、こまめに摂取します。
運動習慣も大切です。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、腸の動きを活発にし、便秘予防につながります。また、骨盤底筋を鍛える体操も、肛門周囲の血流改善に効果的です。
入浴は、ぬるめのお湯にゆっくりつかることで、肛門周囲の血流が改善され、筋肉の緊張もほぐれます。シャワーだけで済ませず、できるだけ湯船につかる習慣をつけましょう。
日常生活で心がけるポイント
排便習慣の改善は痔の予防・治療において重要です。便意を我慢せず、朝食後など決まった時間にトイレに行く習慣をつけます。排便時は前かがみの姿勢をとり、足台を使用すると直腸と肛門の角度が緩やかになり、スムーズな排便が可能になります。
トイレでの滞在時間は5分以内を目安にし、スマートフォンや新聞を持ち込まないようにします。排便後は、ウォシュレットで優しく洗浄し、柔らかいトイレットペーパーで水分を拭き取ります。
仕事中は、1時間に1回は立ち上がり、軽くストレッチをすることで、肛門周囲の血流改善を図ります。クッションを使用する場合は、ドーナツ型のものより、低反発素材の平らなものが推奨されます。
受診すべきサインと症状悪化の目安
排便時の出血が2週間以上続く場合、出血量が増加している場合は要注意です。また、肛門から何かが出てくる感覚がある、肛門周囲に硬いしこりができた、排便時以外にも痛みが続く、発熱や膿の排出がある場合も、速やかな受診が必要です。
特に、40歳以上で初めて肛門からの出血を経験した場合は、大腸がんなど他の疾患の可能性も考慮し、大腸内視鏡検査を含めた精密検査を受けることが推奨されます。
日頃からの生活習慣の改善により、多くの痔は予防可能です。食物繊維と水分を十分に摂り、適度な運動を心がけ、正しい排便習慣を身につけることで、痔のリスクを大幅に減らすことができます。
痔のトラブルは恥ずかしさから受診をためらう方が多いですが、専門医による適切な診断と治療により、多くの場合は改善が期待できます。違和感や異変を感じたら、迷わず肛門科を受診し、快適な日常生活を取り戻しましょう。
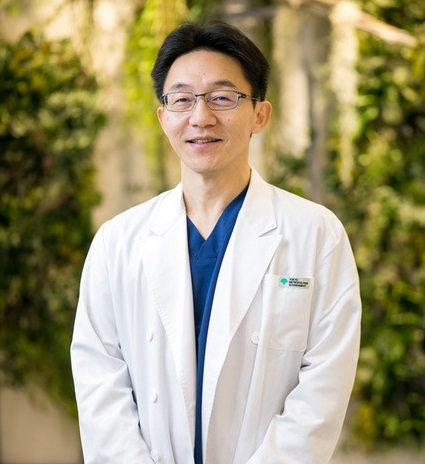
にしおか内科クリニック
院長 西岡 清訓
(にしおか きよのり)
- (元)日本呼吸器外科学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会指導医・専門医
- 日本外科学会専門医
- 麻酔科標榜医・がん治療認定医